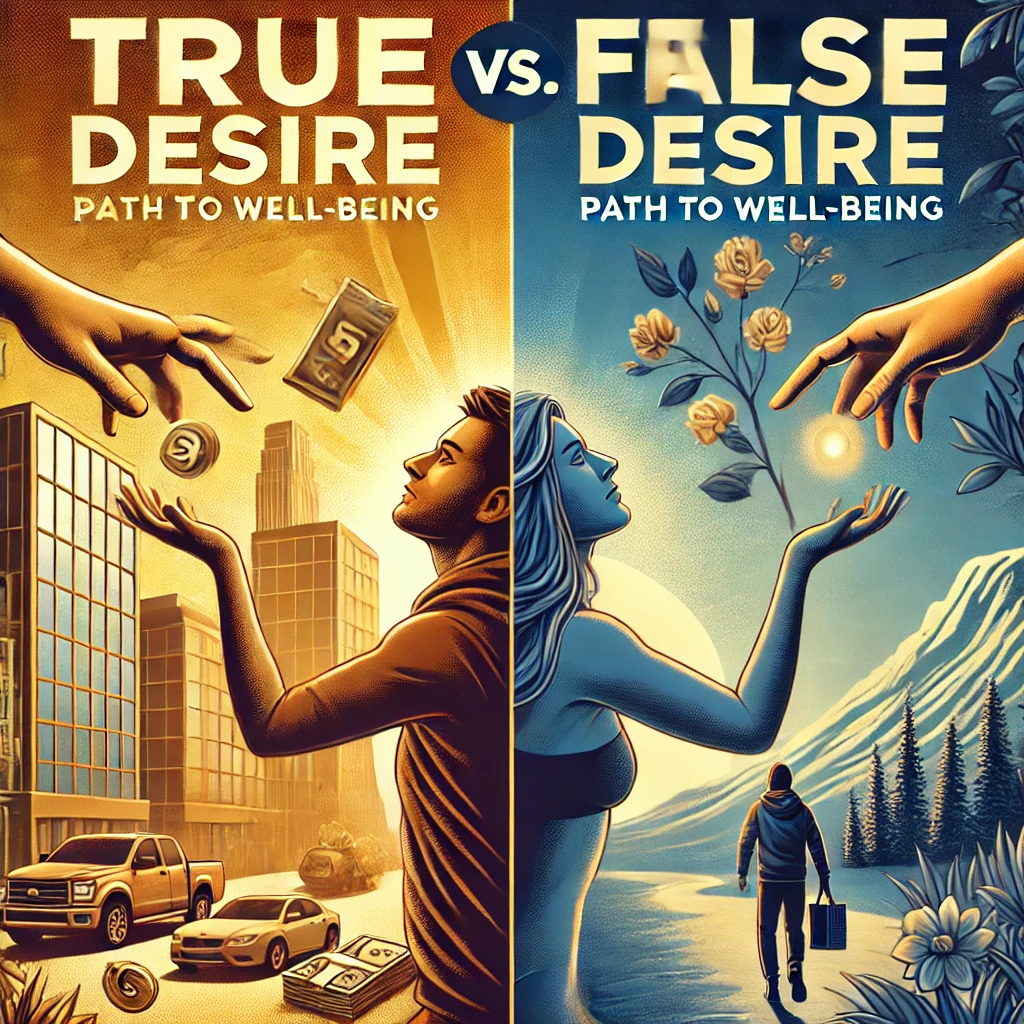1. はじめに
私たちが抱く「欲望」は、実は大きく2種類に分けられると言われています。それが、「本物の欲望(authentic desires)」と「偽物の欲望(inauthentic desires)」。
一見どちらも同じ「欲望」のように思えますが、この2つを見分けられるようになると、人生の満足度や幸福感(ウェルビーイング)が大きく変わってきます。
本記事では、心理学や哲学の観点からそれぞれの欲望を整理し、「なぜ本物の欲望を大切にすることがウェルビーイング向上に役立つのか」をわかりやすく解説します。
2. 「本物の欲望」と「偽物の欲望」とは?
2-1. 本物の欲望(Authentic Desires)
- 自分の内面・価値観に根ざした欲求
心の奥底で「こうしたい」「これを大事にしたい」と強く感じられるもの。 - 自己決定理論における“内発的動機づけ”に近い
例:自分が好きなことや得意なことを伸ばしたい、誰かの役に立ちたい…など、内面的な充実感ややりがいを軸にした欲望。 - 実存哲学の「本来的なあり方」とも対応
自分が本当に望んでいることに気づき、それに基づいて主体的に生きる姿勢。
2-2. 偽物の欲望(Inauthentic Desires)
- 外部の期待や評価に左右される欲求
「周りに認められたい」「SNS映えしたい」「流行だから欲しい」など、他者や社会的な価値観が動機の中心にある。 - 自己決定理論における“外発的動機づけ”
例:お金や地位、名声といった外から与えられる報酬を求め続けるが、達成感が持続しにくい。 - 不一致(Incongruence)を起こしやすい
カール・ロジャーズが指摘する「自己概念」と「本当の自分」のずれを生み、満たされなさを抱えやすくなる。
3. ウェルビーイングへの影響
3-1. 本物の欲望がもたらすプラス効果
- 自己肯定感・充実感の向上
自分の価値観や強みを活かせるため、自然にやりがいや達成感を得られやすい。 - 持続的なモチベーション
“自分が本当に好きなこと”なので、長期間にわたって熱意を持ち続けやすい。 - 良好な人間関係
自分を偽らず行動するため、他者とも誠実に向き合いやすく、信頼関係を築きやすい。
3-2. 偽物の欲望がもたらすマイナス効果
- 不全感・空虚感
外部の評価はいつ変わるかわからず、いくら手に入れても「まだ足りない」と感じやすい。 - モチベーションの維持が難しい
他者の評価が得られなくなると急にやる気を失うなど、アップダウンが激しくなる。 - 自己一致の低下(ストレスの増大)
“本当は望んでいない”という内面の抵抗感から、心理的ストレスや疲労感を抱えやすい。
4. 本物の欲望を見極めるポイント
4-1. 自分の価値観を明確にする
- 価値観ワーク (Values Clarification)
紙に「自分が大切にしたいこと・好きなこと」を書き出し、優先順位をつけてみる。 - 具体例
「健康」「家族との時間」「クリエイティブな仕事」「社会貢献」「自己成長」…どれが自分にとって本当に重要かを再認識する。
4-2. 小さな行動選択でも「本心か?」を確認
- 日常の選択や行動をする前に、自分自身に「これ、本当にやりたいと思ってる?」「誰かに認められたいからやってる?」と問いかける。
- 自分の心の声に気づく訓練を習慣化することで、“外部評価が理由か、自分の内面から湧き出たものか”を判別しやすくなる。
4-3. マインドフルネス・セルフモニタリング
- マインドフルネス
外部の刺激に振り回されず、「いまこの瞬間」に注目して自分の感情や身体感覚を観察。 - セルフモニタリング
認知行動療法(CBT)の手法。思考・感情・行動を記録し振り返ることで、欲望の根っこにある動機を客観的に見つめる。
5. 本物の欲望を追求すると広がるウェルビーイング
5-1. 深い自己実現と「意味」の獲得
- ポジティブ心理学で言う「意味 (Meaning)」を見出しやすくなる。
- アリストテレスのエウダイモニア(人間的な善、充実)やマズローの自己超越と通じる考え方でもあり、自分の本質を活かして生きる満足感が大きくなる。
5-2. 他者貢献・利他性とのつながり
- 本当に好きなことや得意なことを伸ばすと、結果的に社会や周囲の人への貢献につながりやすい。
- “自分が楽しい”ことを周りと共有することで、自分も他者もポジティブな感情を得られる好循環が生まれる。
6. 参考文献・情報源
本記事の内容は、以下の理論や研究知見に基づいています。
- 自己決定理論 (SDT) / 内発的動機づけ
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. Guilford Publications.
- 実存哲学の本来的・非本来的な存在
- Heidegger, M. (1927). Sein und Zeit (Being and Time).
- Sartre, J.-P. (1943). L’être et le néant (Being and Nothingness).
- カール・ロジャーズの自己一致 (Congruence)
- Rogers, C. R. (1961). On Becoming a Person: A Therapist’s View of Psychotherapy. Houghton Mifflin.
- ポジティブ心理学 / PERMAモデル
- 日本ポジティブ心理学協会の解説、Seligman, M. E. P. (2011). Flourish など。
- その他の関連研究
- Kasser, T. (2016). Materialistic Values and Goals. Annual Review of Psychology, 67, 489–514.
- Moller, A. C., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2006). Self-Determination Theory and the Paradox of Happiness. In A. Delle Fave (Ed.), Dimensions of Well-Being (pp. 1–20).
- van Dierendonck, D. (2011). Servant Leadership: A Review and Synthesis. Journal of Management, 37(4), 1228–1261.
まとめ
「なんとなく欲しい」「評価されたいからやる」という偽物の欲望を追いかけていると、どれだけ達成しても満たされず、長続きしないもの。一方で、自分の心から湧き上がる本物の欲望を大切にすると、自己肯定感や充実感が高まり、周囲との関係もより豊かになります。
- まずは自分の価値観を知ることから
- 小さな選択でも「本心かどうか」を問いかける習慣
- マインドフルネスやセルフモニタリングで“今の自分”を客観視
こうしたプロセスを積み重ねていくと、より自分らしい生き方が見えてくるはずです。本物の欲望を軸にウェルビーイングを高め、人生をより豊かにしていきましょう。