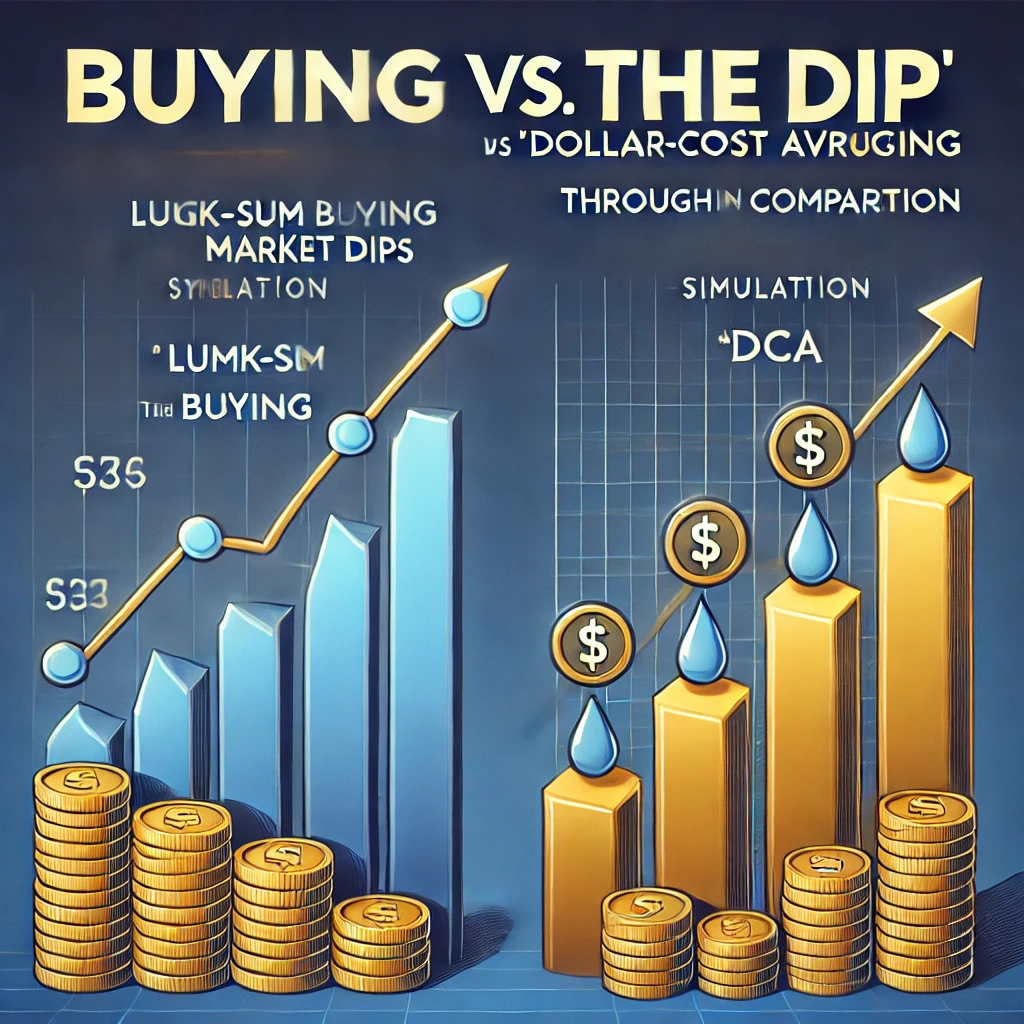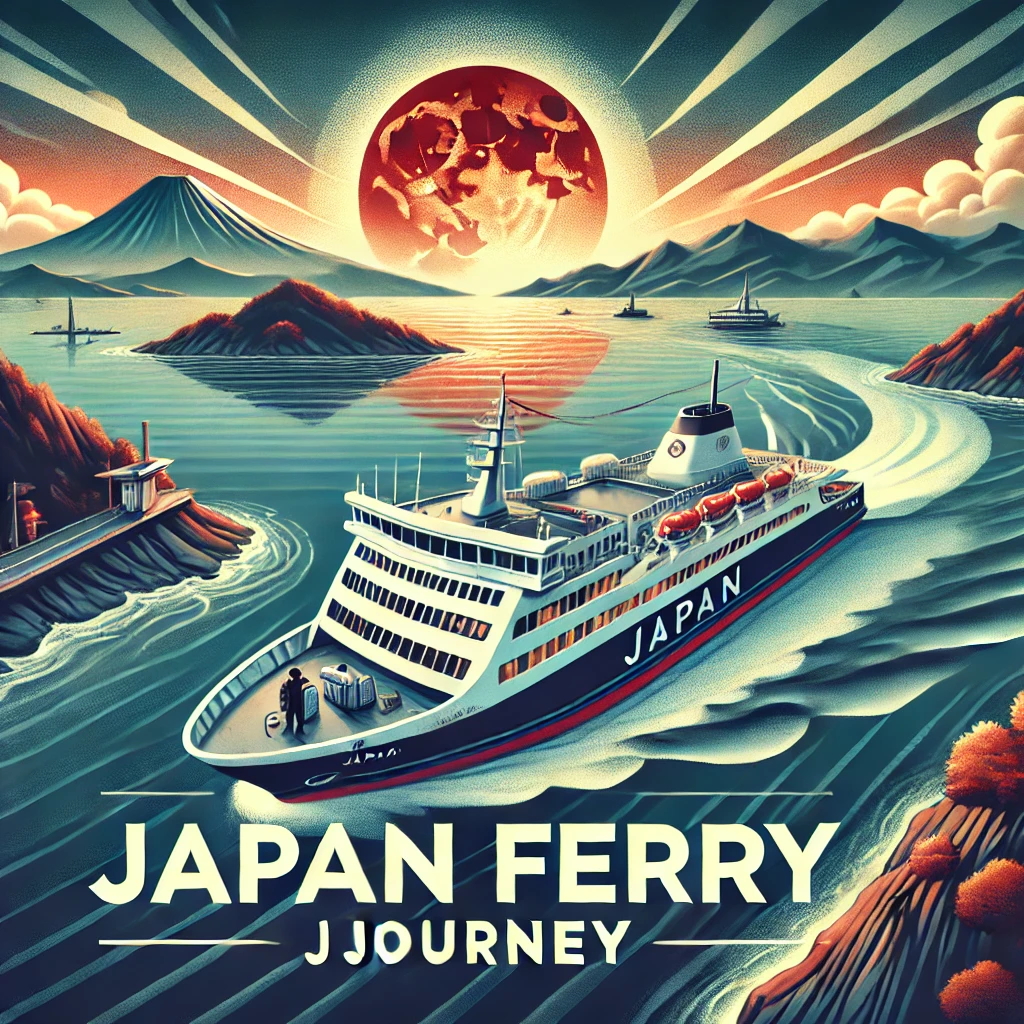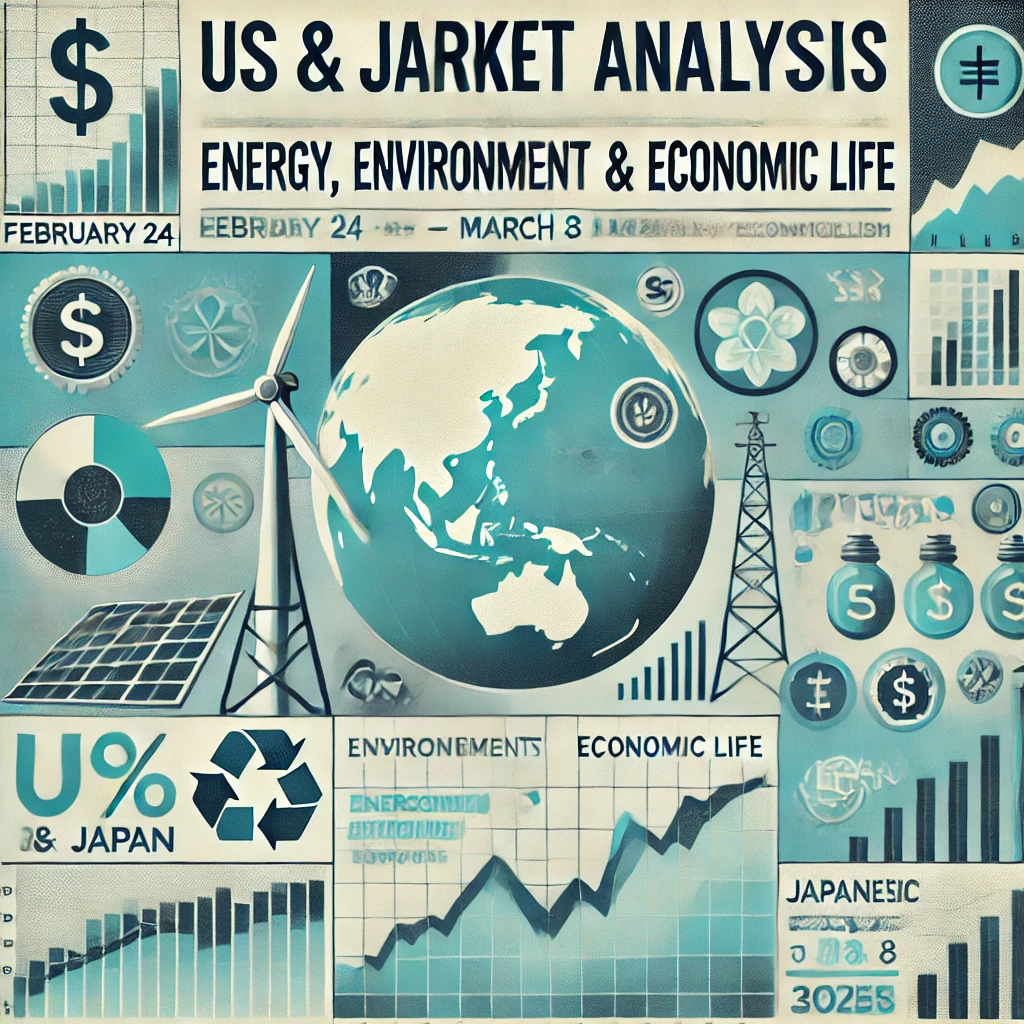以下の記事は、投資判断に用いることを目的としたものではなく、FELIX☆newsが執筆した一個人の感想、コメントとなっています。このため、正確性にかける記述や誤った記述がある可能性があります。また、投資を促すものではありません。必ず最新の公式情報をご確認ください。数字や内容は記事執筆時点(2025年2月16日)での公開データ・報道を元にしていますが、将来的、修正や訂正、変更される可能性がありますのでご注意ください。
株式投資では、株価の下落局面を「チャンス」と捉えるかどうかが大きな分かれ道です。ここでは、株価が下がったときに「買い増し(平均取得単価を下げる)」する手法と、一定額をコツコツ投資する「ドルコスト平均法」の2つに焦点を当て、シミュレーションを通じてメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
1. 買い増しで平均取得単価を下げるシミュレーション
ケース設定
- 最初に購入
- 株価:$100
- 購入株数:10株
- 投資額合計:$1,000
- 平均取得単価:$100
- 株価下落:$60 に下落
- 追加購入(買い増し)
- 株数:10株
- 追加投資額:$60 × 10株 = $600
- 合計投資額:$1,000 + $600 = $1,600
- 保有株数合計:10株 + 10株 = 20株
- 平均取得単価合計投資額合計株数=1,60020=$80 \frac{\text{合計投資額}}{\text{合計株数}} = \frac{1,600}{20} = \$80合計株数合計投資額=201,600=$80
シミュレーション結果
- その後、株価が $90 に回復した場合
- 保有株式の評価額:$90 × 20株 = $1,800
- 利益:$1,800 – $1,600 = $200 のプラス
- 買い増しをしなかった場合(10株のみ保有)
- 保有株式の評価額:$90 × 10株 = $900
- 評価損益:$900 – $1,000 = – $100(マイナス)
上記のように、株価下落時に買い増しをすることで平均取得単価を下げられ、回復時のリターンが大きくなりやすいのが大きなメリットです。
注意点
- 株価がさらに下落するリスク
- 企業の業績が回復しないリスク
買い増しの判断をする際は、「一時的な下落」か「構造的な業績悪化」かを見極めたうえで行うことが重要です。
2. ドルコスト平均法(定期・定額投資)のシミュレーション
ドルコスト平均法とは、同じ金額を定期的に継続して投資していく方法です。購入タイミングを判断しなくてもよいため、初心者にも実践しやすい手法といわれています。
ケース設定
- 毎月 $1,000 を投資
- 投資期間:4ヶ月
- 月ごとの株価:(仮)$100 → $80 → $70 → $90
下表のように、毎月コツコツ積み立てるとしましょう。
| 月 | 株価 | 毎月投資額 | 購入株数(小数点以下切捨) | 投資累計額 | 保有株数累計 | 平均取得単価(参考) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | $100 | $1,000 | 10株 | $1,000 | 10株 | $100 |
| 2月 | $80 | $1,000 | 12株 | $2,000 | 22株 | 約$90.9 |
| 3月 | $70 | $1,000 | 14株 | $3,000 | 36株 | 約$83.3 |
| 4月 | $90 | $1,000 | 11株 | $4,000 | 47株 | 約$85.1 |
- 4月終了時点の合計投資額:$4,000
- 保有株式数:47株
- 株価が$90のときの評価額:$90 × 47株 = $4,230
- 評価損益:$4,230 – $4,000 = +$230
株価が上下しながらも、平均取得単価が平準化されて比較的安定した投資成果を得やすいのが、ドルコスト平均法の特長です。
ドルコスト平均法のメリット
- タイミングを考えなくてよい
資金がある限り、決まったサイクルで自動的に投資できるので、心理的負担が小さくなります。 - 高値掴みリスクの軽減
株価が高いときは少なく、安いときは多く買うことになり、結果的に平均取得単価が下がりやすくなります。
ドルコスト平均法の注意点
- 相場が右肩上がりの場合
最初に一括投資をしていたほうがリターンが高くなるケースもあります。 - 下落相場が長期化した場合
コツコツ買い続けても、企業業績が大きく悪化して株価が戻らない場合には損失を抱え続けるリスクがあります。 - 長期投資向き
短期的な売買で利益を狙うよりも、リスク分散と精神的負担の軽減を目指す投資スタンスに向いています。
3. まとめ
買い増し(平均取得単価を下げる)
- メリット
- 下落時に安値で購入でき、株価回復時のリターンを大きくしやすい
- デメリット
- 相場や企業の下落原因次第では、さらに損失を拡大するリスクも
ドルコスト平均法(定期・定額投資)
- メリット
- タイミングを常に計らなくてよく、心理的負担が小さい
- 平均取得単価が平準化し、高値づかみを回避しやすい
- デメリット
- 一括投資で上昇局面を捉えた方が有利になることも
- 企業の将来性が乏しい場合は下落リスクを抑えられない
重要なのは「投資対象の見極め」と「長期的な戦略」
どちらの手法も、必ず利益が出る保証はありません。投資先の企業やファンドの将来性を十分に調べたうえで、
- 株価下落が一時的か、構造的なものか
- 今後の成長性がどの程度見込めるのか
- 自分の投資目的(短期 or 長期)やリスク許容度はどうか
を総合的に判断することが大切です。
さらに、**「一定額だけでなく一定株数を購入」「上昇相場や大きな下落が数回起こるシナリオを想定する」**など、複数のパターンでシミュレーションを行ってみると、より実践的な投資戦略を立てやすくなります。
参考:複数シナリオの検討を
実際の相場は単純な上下だけでなく、ニュースや経済指標によって大きく乱高下することも多いもの。投資する銘柄が異なれば業種特有のリスクや景気に対する感応度も変わってきます。複数のシナリオを想定したうえで、資金管理やリスク分散を意識しながら投資を続けることが大切です。
免責事項
本記事は、投資に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄の売買や投資を推奨するものではありません。投資に伴う最終的な判断とリスクは、ご自身の責任で行ってください。FELIX☆newsや執筆者は、本記事により生じた損害その他は、一切、責任を負いません。必要に応じて、ファイナンシャルプランナーや投資アドバイザーなど専門家への相談もご検討ください